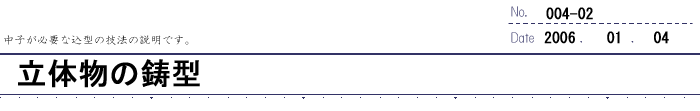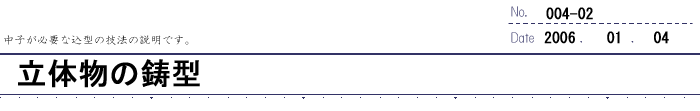|
 |
| 10・外型を焼いて乾燥させる。 |
11・乾燥後の型。これから金属になる部分に裏土を貼っていく。 |
 |
 |
| 12・裏土を貼ったあと、中子砂を込める。中子砂を20mmぐらいの厚さまでよく締め固める。中子のハバキ部分は玉土をつける。 |
13・中子砂を込めたあと、筋金をいれ粗土をつける。そのあと、炭で乾燥させ、中子砂が乾燥後それぞれの張り合わせ面に濃い埴汁を盛る。 |
 |
 |
| 14・上に被せるほうの外型に反面の中子を固定し、下に据える型に被せ中子同士をずれないようにくっつける。くっつけたら、接合部分を修正、乾燥させる。。 |
15・くっつけた中子を慎重に取り出し、壊れた箇所の修正をし、外型と中子の隙間が正確かどうか中子を外型におさめて確認する。よければ黒味を塗って中子の完成。 |
 |
 |
| 16・外型に湯道を掘る。紙土部分には墨汁を塗り、湯道部分には黒味を塗る。 |
17・中子を収める。外型と中子の隙間にホコリガ入らないように慎重に収める。 |
 |
 |
| 18・型を閉じる。上型と下型の筋金どうしを針金で8の字で結ぶ。 |
19・外型と外型の接合線、中子と外型の接合線をしっかりと粗土で目止めし、湯口を作る。 |
 |
 |
| 20・鋳型の完成。このあと窯を築いて焼成し、金属を鋳込む。 |
〜鋳上がったばかりの作品〜 |